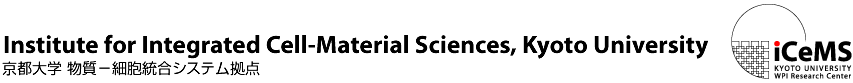堀毛悟史博士、ブリケオ研究員、北川進教授ら、湿度ゼロ環境100度以上で高いプロトン伝導性を示す多孔性固体電解質の合成に成功:ナノ細孔の中で有機分子がプロトンを受け渡す [Nature Mat
2009年9月7日
<研究成果のポイント>
- 有機分子をナノ細孔に配列させる新たな手法により、プロトン伝導性複合材料を合成
- 水分が全くない湿度ゼロ%の環境においても、温度120度で高いプロトン伝導を達成、中温領域のプロトン伝導体として燃料電池の固体電解質に有望
- ナノ細孔における伝導メカニズムを核磁気共鳴測定によって詳細に解明
国立大学法人 京都大学(総長 松本 紘)と独立行政法人 科学技術振興機構(以下JST、理事長 北澤 宏一)の研究グループは、国立大学法人 金沢大学(学長 中村 信一)と協力し、固体中に規則的なナノ細孔を作り、その中にプロトンを持つ有機分子を規則的に配置することにより、湿度ゼロ、100度以上の環境において高い伝導性を持つ燃料電池用の固体電解質を合成することに成功しました。さらに核磁気共鳴(NMR)測定を用い、伝導メカニズムの解析にも成功しました。
京都大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)の北川 進 副拠点長、JST 戦略的創造研究推進事業 ERATO型研究「北川統合細孔プロジェクト」のサリーヤ・ブリケオ 研究員(iCeMS特任研究員)、堀毛 悟史 博士らの研究グループは今回、ナノ孔物質の合成および有機分子の導入によるプロトン伝導性複合体の合成を行い、金沢大学の水野 元博 教授のグループが、NMR測定によりプロトン伝導のメカニズムを分子レベルで解析を行いました。
約1nmサイズの規則的な細孔を持つ多孔性金属錯体を用いると、プロトンを持つ小さな有機分子が高い運動性を保ちながら取り込まれます。そして細孔の中で有機分子が高速で動き回り、その結果プロトンを輸送するようになります。有機分子にイミダゾール分子を用いたところ、この多孔性金属錯体―イミダゾール複合体は100度以上でも安定であり、高いプロトン伝導能を示すことが分かりました。そしてこの合成法が未だ大きな課題である温度範囲(100~300度)、無加湿という環境で作動する燃料電池用の固体電解質の開発において有望であることが分かりました。この有機分子を多孔性金属錯体に導入する手法は、さまざまな組み合わせに簡便に適用でき、新たなプロトン伝導性材料の合成に役立つことが期待されます。
今回の研究は、JST 戦略的創造研究推進事業 ERATO型研究「北川統合細孔プロジェクト」(研究総括:北川 進)の一環として行われ、9月6日(英国時間、日本時間の9月7日)付けの英国科学雑誌『Nature Materials(ネイチャー・マテリアルズ)』オンライン速報版で公開されました。
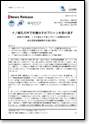 続きを読む (iCeMSニュースリリース|PDF: 564KB) |
 (左から)北川教授、 ブリケオ特任研究員、堀毛研究員 |
<該当論文>
"One-dimensional imidazole aggregate in aluminium porous coordination polymers with high proton conductivity"
Sareeya Bureekaew, Satoshi Horike, Masakazu Higuchi, Motohiro Mizuno, Takashi Kawamura, Daisuke Tanaka, Nobuhiro Yanai & Susumu Kitagawa
Nature Materials, Published online: 6 September 2009 | doi:10.1038/nmat2526
<関連記事・報道>
 読売新聞(2009年10月26日 11面)
読売新聞(2009年10月26日 11面)- 朝日新聞(2009年9月29日 21面)
- 科学新聞(2009年9月11日 1面)
 京都新聞(2009年9月7日 22面)
京都新聞(2009年9月7日 22面) 産経新聞(2009年9月7日 2面)
産経新聞(2009年9月7日 2面)- 日本経済新聞(2009年9月7日 13面)
 47News|共同通信(2009年9月7日 Web)
47News|共同通信(2009年9月7日 Web)
に掲載されました。