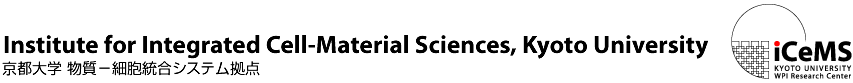最先端・次世代研究開発支援プログラムに上杉志成教授、原田慶恵教授、見学美根子准教授、上野隆史准教授、仙石慎太郎准教授が採択
2011年2月14日
京都大学物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)の上杉志成教授、原田慶恵教授、見学美根子准教授、上野隆史准教授、仙石慎太郎准教授の研究課題が10日、世界をリードする研究を支援する制度「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択されました。
同プログラムは政府の総合科学技術会議(議長:菅直人首相)が、主に若手・女性・地域の研究者への研究支援と、グリーン・イノベーション及びライフ・イノベーションの推進を目的として創設したものです。
![]() 同会議の発表によると、応募数5,618件のうち329件が採択され、配分額の合計は約486億円となります。iCeMSの採択課題5件の詳細は、以下のとおりです。
同会議の発表によると、応募数5,618件のうち329件が採択され、配分額の合計は約486億円となります。iCeMSの採択課題5件の詳細は、以下のとおりです。
上杉志成 教授
課題名「合成小分子化合物による細胞の操作と分析」

- 研究の背景:人類の歴史の中で、生き物に作用する化合物は主に3つの用途に使われてきました。医薬品、農薬、研究用試薬です。この研究では、新しい第4の用途として、化合物の細胞治療への利用を提案します。化合物は医薬品として人類の健康に貢献してきましたが、化合物医薬だけでは治らない病気があります。そんな難病に細胞治療が期待されています。
- 研究の目標:この研究の目的は、これまで人類が経験したことがない全く新しい化合物の使い方を検証することです。その一つとして化合物の細胞治療への利用に挑戦します。この実現には、まず、人間の細胞の基本的な性質を操る化合物を見つけ、化学合成しなければなりません。細胞の営みはせんじつめれば、化学反応で成り立っています。それなら、逆に化学の力で細胞を自由に操れるはずです。
- 研究の特色:化学と細胞治療という日本の強い分野が融合した研究です。化学と生物学の最新技術を組み合わせ、世界初の化合物を次々と開拓します。前人未踏の化合物によって、基礎研究と応用研究の両方が実現できます。
- 将来的に期待される効果や応用分野:近い将来、細胞治療はより頻繁に病院で行われる治療になります。問題は高コストです。工場で生産できる安価で安定な化合物を使って細胞治療を効率化すれば、コスト削減と安全性の向上が実現できます。
原田慶恵 教授
課題名「蛍光ダイアモンドナノ粒子を使った新規1分子イメージング法の開発と生体分子観察」

- 研究の背景:生体分子が機能するしくみを明らかにすることは、生命活動を知る上で非常に重要です。そのため、生体分子に“光る物質”(蛍光物質)をつけて、それを目印として1個1個の生体分子の動きや構造変化を顕微鏡で観察する研究が行われています。しかし、現在目印として使われている蛍光物質には、安定性が悪く長時間観察できない、生体内に混在する他の発光物質と区別できない、回転運動を観察できないなどの難点があります。
- 研究の目標:新しい蛍光物質として、生体分子の大きさと同程度の小さなダイヤモンド粒子(ダイヤモンド内に炭素の代わりに入り込んだ窒素と炭素の欠失が近接して存在すると蛍光物質のように光る)を使った新規蛍光イメージング技術を開発し、生体分子の観察に適用する手法を確立します。
- 研究の特色:この新しい蛍光物質は、従来使われている蛍光物質の難点をすべて克服することができる優れた性質を持ちます。そのため、これまで観察することができなかった個々の生体分子の動きや構造変化を検出することが可能になります。
- 将来的に期待される効果や応用分野:生体分子が機能するしくみについて新しい知見が得られ、生命現象の理解が深まる他、それらの機能不全を原因とする疾病に対する創薬や治療に重要な情報を提供します。
見学美根子 准教授
課題名「臨界期可塑性によるニューロン樹状突起形態変化と神経回路再編成の機構」

- 研究の背景:ヒトを含む高等動物の脳は、外界の環境に適応して神経回路の配線や効率を変え、柔軟に行動パターンを修正します。特に臨界期と呼ばれる生後発達期の一定期間には、外界の刺激により遺伝的プログラムで規定された回路の書換えが頻繁に起り、最適化された回路が成体まで維持されることが知られていますが、臨界期の分子基盤はまだほとんど明らかになっていません。
- 研究の目標:小脳ニューロンの活動依存的な突起パターンの再編成現象をモデルとして、臨界期脳における神経細胞の形態変化と神経回路の再編成の分子機構を明らかにします。
- 研究の特色:解剖学・生理学の知見が蓄積しているマウス小脳を用い、分子遺伝学、分子解剖学、電気生理学、細胞生物学などの階層横断的方法論を融合させることで、細胞形態の変化が局所神経回路の再編成をおこし、個体行動の制御に至るしくみを総合的に理解することが可能となります。
- 将来的に期待される効果や応用分野:臨界期機構が関与するとされる適応不全を伴う精神神経疾患(うつ病・統合失調症・自閉症など)の病態理解と病因解明に貢献できる可能性があり、また損傷脳の機能回復の再生治療やリハビリテーションへの応用などの波及効果が期待されます。さらに脳発達に効果的な幼児教育の開発に貢献できる可能性があります。
上野隆史 准教授
課題名「バイオ固体材料の生体ガス分子応答による細胞機能制御」

- 研究の背景:近年の高齢化、医療負担増といった深刻な社会問題の解決策の一つとして、細胞機能制御法の技術開発が緊急課題となっています。国内外では、ポリマーや蛋白質、ペプチドを骨格とした材料の研究が進められているものの、生体親和性や、安定性、刺激応答性などで問題点を抱えており、革新的な高機能材料の開発が求められています。
- 研究の目標:細胞の代謝制御に関与する生体ガス分子(酸素、一酸化炭素、一酸化窒素等)に着目し、それらの分子を吸脱着、分解、生成する次世代材料の作製によって細胞機能制御を達成します。
- 研究の特色:本研究では、細胞が生産する特殊な蛋白質によって形成される固体材料を用います。この材料には、異なる複数の生体ガス分子と反応する蛋白質やペプチドを同時に組み込むことが可能であり、これまでにない高機能化が実現出来ます。
- 将来的に期待される効果や応用分野:ライフ・イノベーションの要である細胞機能制御の新しい手法を提供し、iPS(人工多能性幹)細胞やES(胚性幹)細胞の評価システムに組み込む事により、脳梗塞、アルツハイマー病、発癌、肝臓疾患等の医薬品開発への応用、さらには、過酷な条件を必要としない再生可能なものづくりへ革新的なブレークスルーを与えるものと期待されます。
仙石慎太郎 准教授
課題名「幹細胞科学技術の統合的イノベーション・マネジメント研究と人材育成・事業化支援」

- 研究の背景:幹細胞は再生医療や創薬の鍵となる科学技術であり、日本はiPS(人工多能性幹)細胞の発見などの優れた成果を輩出しています。一方、イノベーション(科学技術の活用)となると、欧米主要国はもとより、いくつかの新興国よりも劣勢です。これは、イノベーションの「種」の発見には熱心だった反面、「育て方」の研究・考察が必ずしも十分でなかったことによります。
- 研究の目標:幹細胞分野における京都大学の世界的な影響力とネットワークを基盤とし、イノベーション経営(マネジメント)の方法論を開発します。そして企業等と協力し、事業の創出を図ります。
- 研究の特色:これまでは経験則に頼りがちだったイノベーションの検討に、科学的なアプローチを導入します。人文社会科学と幹細胞科学の研究者が密接に協力し合い、論文・特許データの詳細分析と、国内外の産業クラスター構造の比較分析を行い、世界の動向と日本の強み・弱みを正確に把握します。
- 将来的に期待される効果や応用分野:日本の「ものづくり」の強みが発揮できる製品・サービス分野の開拓、日本の環境に適した事業化モデルの開発を通じて、イノベーションの着実な実現が図られます。また、この方法論を他分野にも展開することで、新産業育成への幅広い貢献も期待できます。