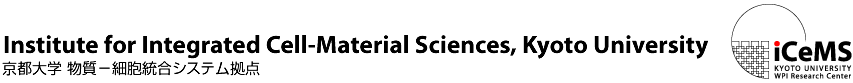中辻憲夫教授と仙石慎太郎准教授、エルゼビア社の幹細胞研究報告書に共著者として貢献:分野の世界動向と展望を調査

2013年12月4日
![]() エルゼビア、
エルゼビア、![]() EuroStemCell、および京都大学 物質―細胞統合システム拠点(以下iCeMS)は、
EuroStemCell、および京都大学 物質―細胞統合システム拠点(以下iCeMS)は、![]() 世界幹細胞サミット(以下WSCS)で、幹細胞研究の動向と展望をまとめた報告書「
世界幹細胞サミット(以下WSCS)で、幹細胞研究の動向と展望をまとめた報告書「![]() Stem Cell Research: Trends and Perspectives on the Evolving International Landscape」(以下レポート)を発表しました。本レポートは、成長著しい幹細胞研究全般を網羅的に分析しつつ、さらにES細胞・ヒトES細胞・iPS細胞について、国レベルおよび研究大学/研究機関レベルの研究動向比較、共同研究状況などを調査したものです。
Stem Cell Research: Trends and Perspectives on the Evolving International Landscape」(以下レポート)を発表しました。本レポートは、成長著しい幹細胞研究全般を網羅的に分析しつつ、さらにES細胞・ヒトES細胞・iPS細胞について、国レベルおよび研究大学/研究機関レベルの研究動向比較、共同研究状況などを調査したものです。
客観的データに基づき広範かつ透過的に研究活動を明らかにするため、本レポートでは研究をリードしている各国の論文発表や被引用度、共同研究の度合いなどの分析データを用い、国家間の重点領域や成長度合いについて調査しました。対象論文データの収集にはエルゼビアの世界最大級の抄録・引用文献データベースScopus(スコーパス)を使用し、科学者や政策関係者からの意見として研究の現状および将来の希望を含めた多様な見解が示されています。本レポートの知見は、WSCSの最終日12月6日に、中辻憲夫と仙石慎太郎(京都大学iCeMS)、Stephen Minger (GE Healthcare)、Brock C. Reeve(Harvard Stem Cell Institute)、Deborah J. Sweet(Cell Press)、Brad Fenwick(Elsevier)により発表される予定です。
本レポートの主な内容を以下に抜粋します:
- 幹細胞研究分野の論文総増加率は年7パーセントで、世界平均の2.9パーセントの倍以上。特に2012年にノーベル医学・生理学賞を受賞したiPS細胞の研究分野の論文数の増加は目覚ましく、2008年からの成長率は77パーセント。
- 幹細胞関連の論文は、分野補正後の相対被引用度(field weighted citation impact: FWCI)による世界平均と比べて1.5倍多く引用される傾向がある。ES細胞論文の相対被引用度は平均1.8以上を維持(2008-2012年)、ヒトES細胞論文は2008年の2.35から2012年は2.08に減少、成長著しいiPS細胞関連は幹細胞分野の最高数値で、FWCIは2.93(2008-2012年)。
- 幹細胞関連論文の約半数が「drug development(創薬)」または「regenerative medicine(再生医療)」に関連したキーワードを含んでおり、現在臨床での応用を目指した研究が活発であることを表している。幹細胞論文では「regenerative medicine」が47パーセント、「drug development」が2パーセント程度、キーワードとして含まれている。一方iPS細胞論文では「drug development」が11パーセントに上り、被引用度も高い。
- 幹細胞研究が国内で相対的に活発なのはシンガポール、イタリア、米国、日本、イスラエルで、論文の絶対数は米国と中国が最多。
幹細胞研究は、新たな医療の可能性をもたらします。これまで治療が難しいとされていた疾患や重篤な損傷の新たな治療法の開発が期待されており、2006年にiPS細胞が発見されてからは、創薬から人工細胞までを視野に入れたあらゆる研究活動が一段と活発になっています。世界各国がこの分野を優先課題の一つに掲げる一方で、国ごとに独自の倫理と規制をめぐる議論に基づく科学政策が立案されており、研究活動への影響も想定されます。
iCeMSの設立拠点長である中辻憲夫教授は、「今後ヒト多能性幹細胞が本格的に医療と創薬に実用化されるためには、多分野に跨がる学際的研究に加え、産官学の本格的な連携が必要です。高品質の多能性幹細胞や使用目的に応じた分化細胞の大量培養と生産システムの確立などによる、安全性や信頼性の高レベル確保が重要な課題となります。また、研究開発に対する適切な支援と加速を実現するには、各国政府が複眼的に世界のトレンドを把握し、客観的データに基づいて政策を立案することが重要です」と述べています。
EuroStemCellのプロジェクト・コーディネーターであり、エジンバラ大学再生医療センター医学研究審議会メンバーおよび組織幹細胞生物学のClare Blackburn(クレア・ブラックバーン)教授は、「このレポートは世界の幹細胞研究を俯瞰することができ、より踏み込んだ書誌計量学により国単位および国際レベルの研究トレンドが分かります。例えば、幹細胞研究に強い地域や急拡大している組織というのはどこなのか、各国の研究資金政策は高インパクトの成果をもたらしているのか、といったことを読み取ることができます。示唆に富むこれらの情報を分析することは大変刺激的でした。読者の皆様にとっても、未来の科学政策に影響を与えうる研究分野の理解を深める一助になればと思います」と述べています。
「このレポートの目的は、網羅的な分析を専門家の知見に照らして概観することで、幹細胞研究の科学政策立案を支援することにあります。エルゼビアはEuroStemCellと京都大学iCeMS、およびその専門家の皆様の叡智によりレポートを作成することができ、大変光栄に思っています」とエルゼビアのSciVal製品担当(AGIM)マネージング・ディレクターNick Fowler(ニック・ファウラー)は述べています。
EuroStemCellについて
EuroStemCellは2010年3月に設立され、欧州委員会の第7次研究枠組み計画(Seventh Framework Programme: FP7)の資金により運営、ヨーロッパの90以上の幹細胞および再生医療の研究機関を統合してEU市民に対する幹細胞研究の啓蒙活動を行っています。EuroStemCellは科学者、臨床医、倫理学者、社会学者およびサイエンスコミュニケータ―と提携し、教員や患者代表と緊密に活動しています。
エルゼビアについて
![]() エルゼビアは、科学・技術・医学分野の製品およびサービスを専門とする、世界有数の学術出版社です。科学・医療コミュニティとグローバルに連携して
エルゼビアは、科学・技術・医学分野の製品およびサービスを専門とする、世界有数の学術出版社です。科学・医療コミュニティとグローバルに連携して![]() The Lancetや
The Lancetや![]() Cellを含む2,000 誌以上のジャーナル、MosbyやSaundersの百科事典を含む20,000点を超える書籍を刊行しています。電子製品としては、
Cellを含む2,000 誌以上のジャーナル、MosbyやSaundersの百科事典を含む20,000点を超える書籍を刊行しています。電子製品としては、![]() ScienceDirect、
ScienceDirect、![]() Scopus 、
Scopus 、![]() SciVal、
SciVal、![]() Reaxys、
Reaxys、![]() ClinicalKey、
ClinicalKey、![]() Mosby’s Suiteなどを提供し、科学と医療の専門家の生産性向上や、研究・医療機関におけるよりよい成果の実現、コスト効率の良い運営を支援しています。
Mosby’s Suiteなどを提供し、科学と医療の専門家の生産性向上や、研究・医療機関におけるよりよい成果の実現、コスト効率の良い運営を支援しています。
![]() エルゼビアは、オランダのアムステルダムに本社を置き、社員7,000名を抱えるグローバル企業です。
エルゼビアは、オランダのアムステルダムに本社を置き、社員7,000名を抱えるグローバル企業です。![]() リード・エルゼビア・グループの傘下企業で、世界でもトップクラスの出版社かつ情報プロバイダーです。Reed Elsevier PLC とReed Elsevier NVによって共同保有されています。リード・エルゼビア・グループのティッカーシンボル(証券コード)は、REN(Euronext Amsterdam)、REL(ロンドン証券取引所)、RUK およびENL(ニューヨーク証券取引所)です。
リード・エルゼビア・グループの傘下企業で、世界でもトップクラスの出版社かつ情報プロバイダーです。Reed Elsevier PLC とReed Elsevier NVによって共同保有されています。リード・エルゼビア・グループのティッカーシンボル(証券コード)は、REN(Euronext Amsterdam)、REL(ロンドン証券取引所)、RUK およびENL(ニューヨーク証券取引所)です。