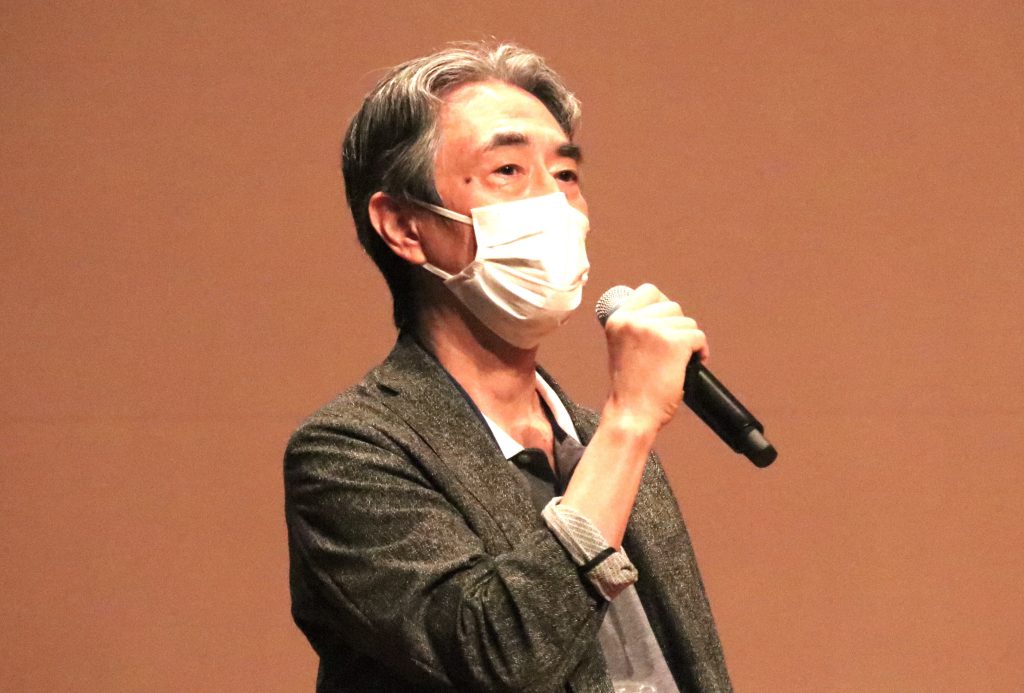第12回iCeMSリトリートを開催しました

9 月 14 日、アイセムスの3 年ぶりの対面でのリトリートが、京都大学百周年時計台記念館で開催され、コロナ以前のような宿泊を伴う研究合宿ではないものの、丸一日かけて学術交流を行いました。
谷口雄一教授が幹事として企画した今回のリトリートは、「Linking Chemical and Biological Science(生物学と化学をつなげる)」と題し、アイセムスで働く生物学と材料科学の研究者のつながりをさらに深めることを目指しました。参加者らは、垣根を越えた研究交流を目標に、自分とは異なる分野の研究者にも伝わる研究発表に取り組みました。
基調講演を行った北川進拠点長は、「(iCeMSが設立された)2007年当時、京都大学では材料科学と生物学は全く別の分野でした。」と述べ、世界の共同研究ネットワークの図を示しながら、アイセムスが設立以降、生物学と材料科学の融合ネットワークに貢献してきたことを強調しました。そして、若手PIの数を増やし、独立した研究を促進することで、研究者らがインスピレーションを追求し続けられるよう拠点形成を続けて行くことを語りました。
続いて、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM)拠点長の吉村崇教授が特別講演を行いました。ITbMもまた、化学と生物学を結びつけ、革新的な生体分子の創製に取り組んでいます。講演に先立ち吉村教授は、アイセムスを ITbM の兄・姉になぞらえ、「皆さんから多くのことを学ぶことを楽しみにしている」と述べ、続いて、様々な動物種やヒトにおける概日リズムや発情・月経周期に焦点を当てた、生物時計の研究に関する講演を行った。
続いて講演した近畿大学の杉本邦久教授は、今年3月までアイセムスのPIを務め、4月から近畿大学に着任しています。杉本教授は、現在近畿大学で行っている、最先端のスーパーセラミックス材料の研究について紹介しました。
昼食後は、グループアクティビティとして、8名程度のチームに分かれてクイズに挑戦。雑学問題や論理問題を解いたり、アイセムスの設立当初の事務部の場所などあまり知られていないキャンパスの名所を探したりしながら、チームメンバーと交流を深めました。3チームが同点で勝ち残り、最後はジャンケンで勝者が決定されました。
午後の最初のセッションでは、生物学の鈴木淳教授と化学の古川修平教授が2人でステージに立ち、アイセムスで行われている融合を表現したヒップホップソング「Fusion」を披露しました。さらに、それぞれが相手のスライドを初見でプレゼンするというチャレンジを行い、互いに分野の境界を超えた理解があることを示しました。
次に登場した、マクダイアミッド研究所のJustin Hodgkiss 教授とiCeMS 京都ジュニアフェローThiadarat Imyen 助教は、それぞれ、アイセムスがニュージーランドとタイに設立した国際共同ラボに深く関わっており、その研究内容や、アイセムスとの国際連携について紹介しました。
続くポスターセッションでは、およそ60名の若手研究者が発表を行い、会場は活気に溢れました。まず、30 名の化学系研究者が、生物系の研究者を聴衆に研究のプレゼンテーションを行い、活発な議論の後、生物系の研究者は化学系の発表のうち、気に入った一つに投票。その後、役割を交代し、生物系の研究者が発表を行い、化学系の研究者が聴衆・評価役に回りました。それぞれの分野で最も多くの票を集めた発表が表彰されました。
最後の学術セッションでは、化学系研究者に向けた生物系の研究発表を川上 巧特定助教(見学グループ)とキム・スヨン研究員(谷口グループ)が、生物系研究者に向けた化学系の発表を、ベヘナム・ガリ准教授(シバニアグループ)と吉村 柾彦 特定助教(藤田グループ)が行いました。
閉会前には、共同幹事の玉野井グループから松本光太郎特定助教がグループアクティビティとポスターセッションの受賞者を発表し、北川拠点長より受賞者に商品が渡されました。
最後に、植田和光研究支援部門長が、閉会の挨拶で対面でのリトリートの成功について感謝を述べました。
ポスター賞受賞者
化学分野:
- Detao Qin (Sivaniah Group) “Organized Microfibrillation As a New Platform for Printing Microfluidic Devices”
- Zaoming Wang (Furukawa Group) “Evaluation of Metal-Organic Framework Membranes for Water Pollutant Testing”
- Kosuke Yasui (Fukazawa Group) ”Concise Synthesis of Novel Electron-Accepting Small-Molecule Organic Materials Composed of Nitrogen-Containing Cross-Conjugated π-Conjugated Skeleton”
生物学分野:
- Rebecca Jimenez (Kengaku Group) “Surface Topography Affects Neuronal Process Orientation and Morphology”
- Jin Shuyu (Uesugi Group) “Self-assembling small-molecule adjuvants as antigen nano-carriers“
- Yuki Yamato (Suzuki Group) “Establish of unwanted cell removal system”
- Mahima Kumar (Namasivayam Group) “Repurposing nucleic acid-based tools for cellular rejuvenation”
- Olivier Kaakeh (Kamei Group) “Microfluidic system mimicking the interaction between endometrium and HG-Blastoid tissues for study of mechanisms of fertilization at the implantation stage”